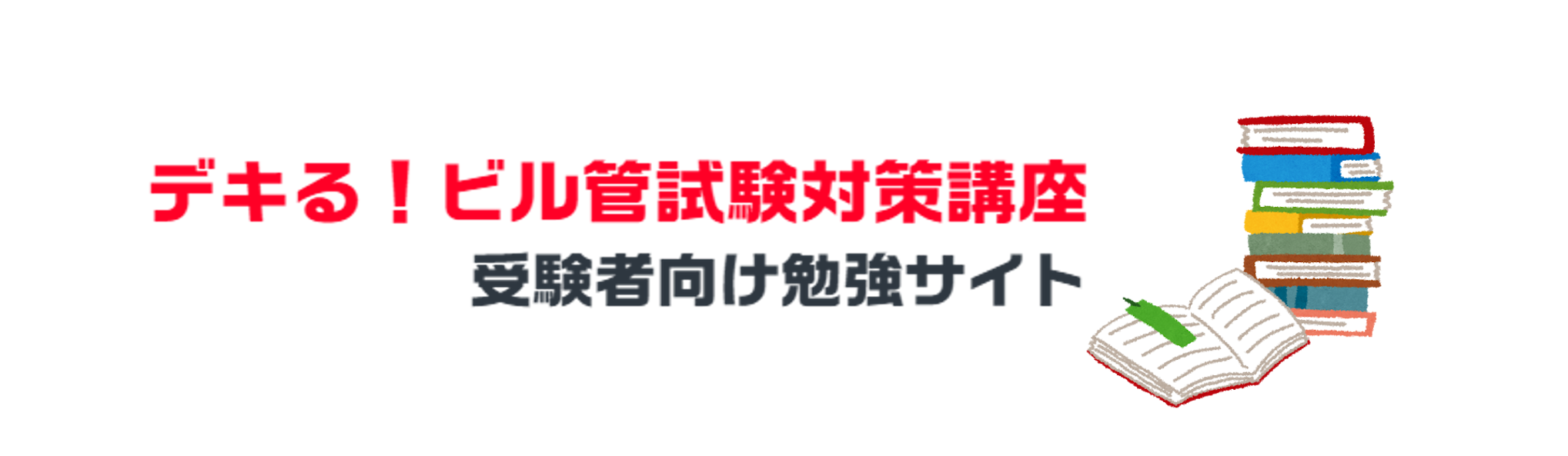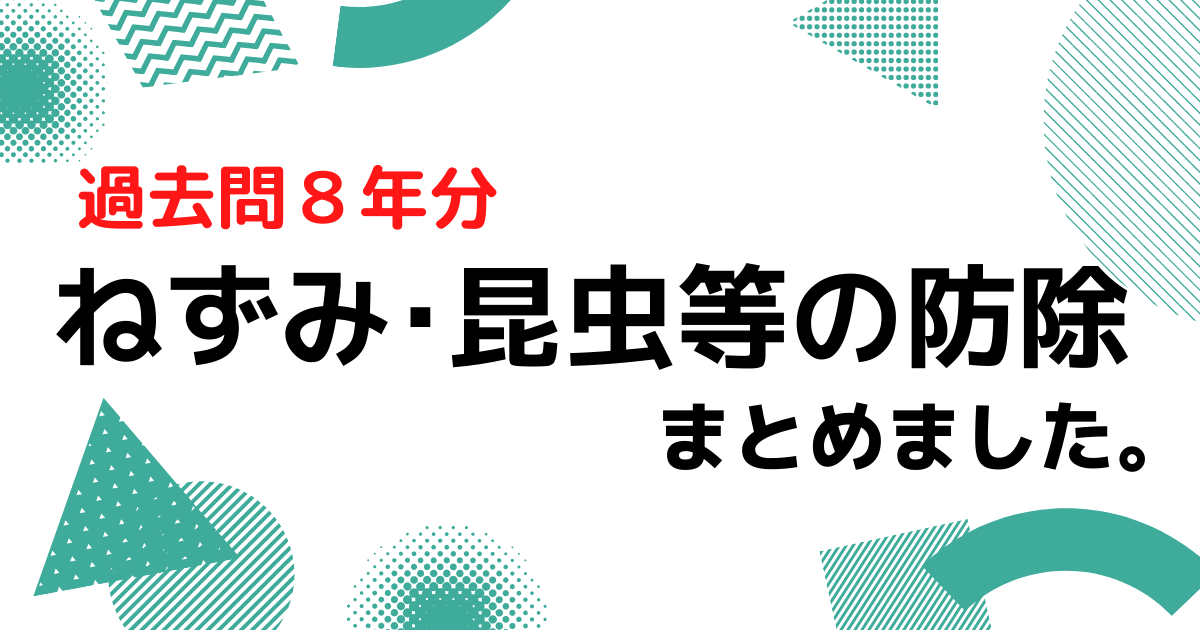ネズミの防除
- 防除は、発生時対策より発生予防対策(発生源対策・侵入防止対策)に重点を置いて実施する。
- 防虫・防鼠構造は、建築物の新築時に設計段階で取り入れるべきせある。
- 侵入防止には自動開閉式のドアが有効。
- 外壁には、ツタ等の植物を這わせたり、樹木の枝を接触させない。
- 侵入を防ぐために、通風口や換気口の金属格子の目の幅を1センチ以下にする。
- 防除は、餌を断つこと、巣の作らせないこと及び通路を遮断することが基本である。
- ネズミは超音波防鼠機に慣れる。
- 捕獲効果を上げるため、餌をつけたうえで数日間はトラップが作動しないようにする。
- 食料取り扱い区域などのネズミが発生しやすい場所では、2か月に1回生息状況調査を行う。
- ねずみ・昆虫等に対する対策を行った場合は、対象生物の密度調査などにより、その効果について客観性のある評価を行う。
- ねずみ等の防除において、IPM(総合的有害生物管理)の理念に基づく防除を実施しなければならない。この防除においては、生息密度調査や防除目標の設定、防除法の選定、生息指数による評価等が重要視され、防除法の選定においては、発生予防対策や侵入防止対策を優先的に検討する必要がある。(黄色の箇所の組み合わせが出題されました。)
殺鼠剤関連
- 抗凝血性殺鼠剤
- 第一世代(継続摂取で効果。遅効性):ワルファリン、クマテトラリル、フマリン
- 第二世代(1回の投与で効果。即効性):ジフェチアロール
- 急性殺鼠剤(1回の投与で致死)
- シリロシド、リン化亜鉛
- 忌避剤
- カプサイシン・シクロヘキシミドはケーブルなどのかじり防止の目的で使用する。
- 殺鼠剤は、経口的な取り込みにより発揮される(経皮的な薬剤はない)
- 喫食性の良い餌を確認するため、毒餌配置前2-3日間は何種類かの餌材で予備調査を行う。
- 粉剤は、ネズミの嗜好に合わせた毒餌製作に使用することができる。
- 喫食性の良い餌を確認するため、毒餌配置前2-3日間は何種類かの餌材で予備調査を行う。
- 殺鼠剤の多くは、選択的毒性が低く、人に対しても強い毒性を示す成分が多い。
- しかし、殺鼠剤の有効成分の濃度は低く抑えられているので、人とネズミの体重差から誤食による人体への影響は少ない。
- 抗凝血性殺鼠剤に対する抵抗性を獲得したネズミの集団がある(淘汰による抵抗性獲得)
- 殺鼠剤の安全性は、毒性の内容や強弱、摂取量、摂取期間によって決まる。
- 毒薬・劇薬指定の殺鼠剤はない。
- 第一世代の抗凝血性殺鼠剤に抵抗があっても、第二世代の殺鼠剤は有効である。
- ブロマジオロン製剤(第二世代の殺鼠剤)は、建築物衛生法に基づく特定建築物内では使用できない。
- ジフェチアロールは、ワルファリンに抵抗性を示すネズミ対策用に開発された。
- 建築物衛生法に基づく特定建築物内での使用が認められている。
- ジフェチアロール以外の抗凝血性殺鼠剤は、連続して喫食させる必要がある。
- カプサイシンのスプレーやパテは、ケーブルなどのかじり防止やネズミによってかじられた穴の修復に使用される。
事後処理
- 殺鼠剤により死亡したネズミから、ハエなどが発生することがある。
- 殺鼠剤による駆除を行った際、イエダニによる吸血被害が顕在化することがある。
- 配置された餌から、貯穀害虫や食品害虫が発生することがある。

デキビル
クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの特徴は重要ポイントです。防除に関する事項は多いですが、基本的な事項なので覚えましょう。