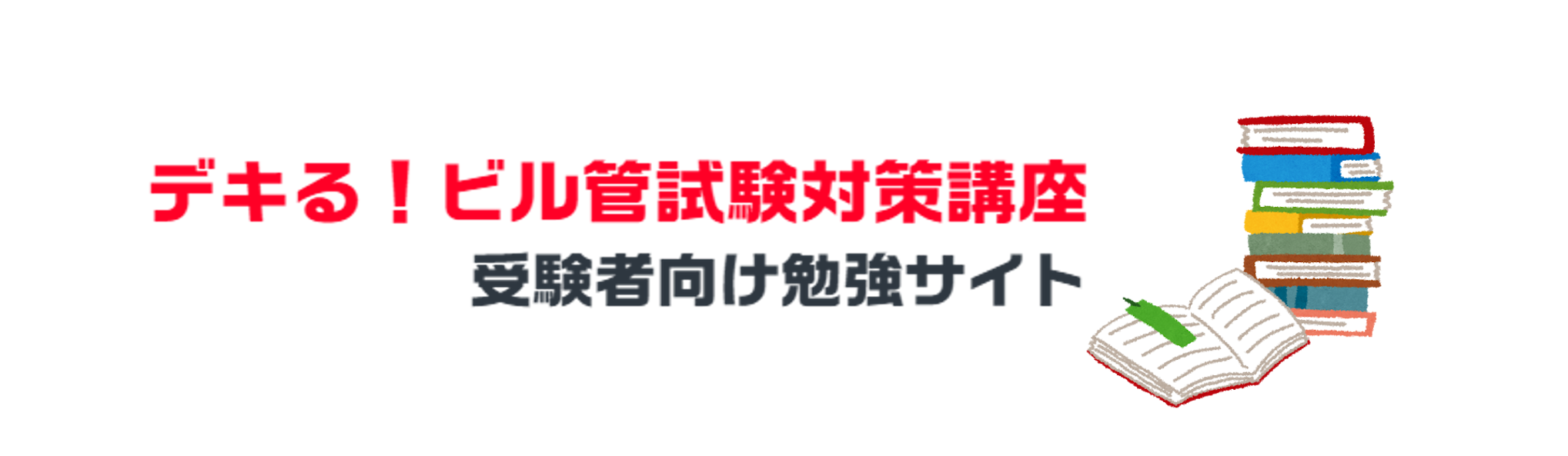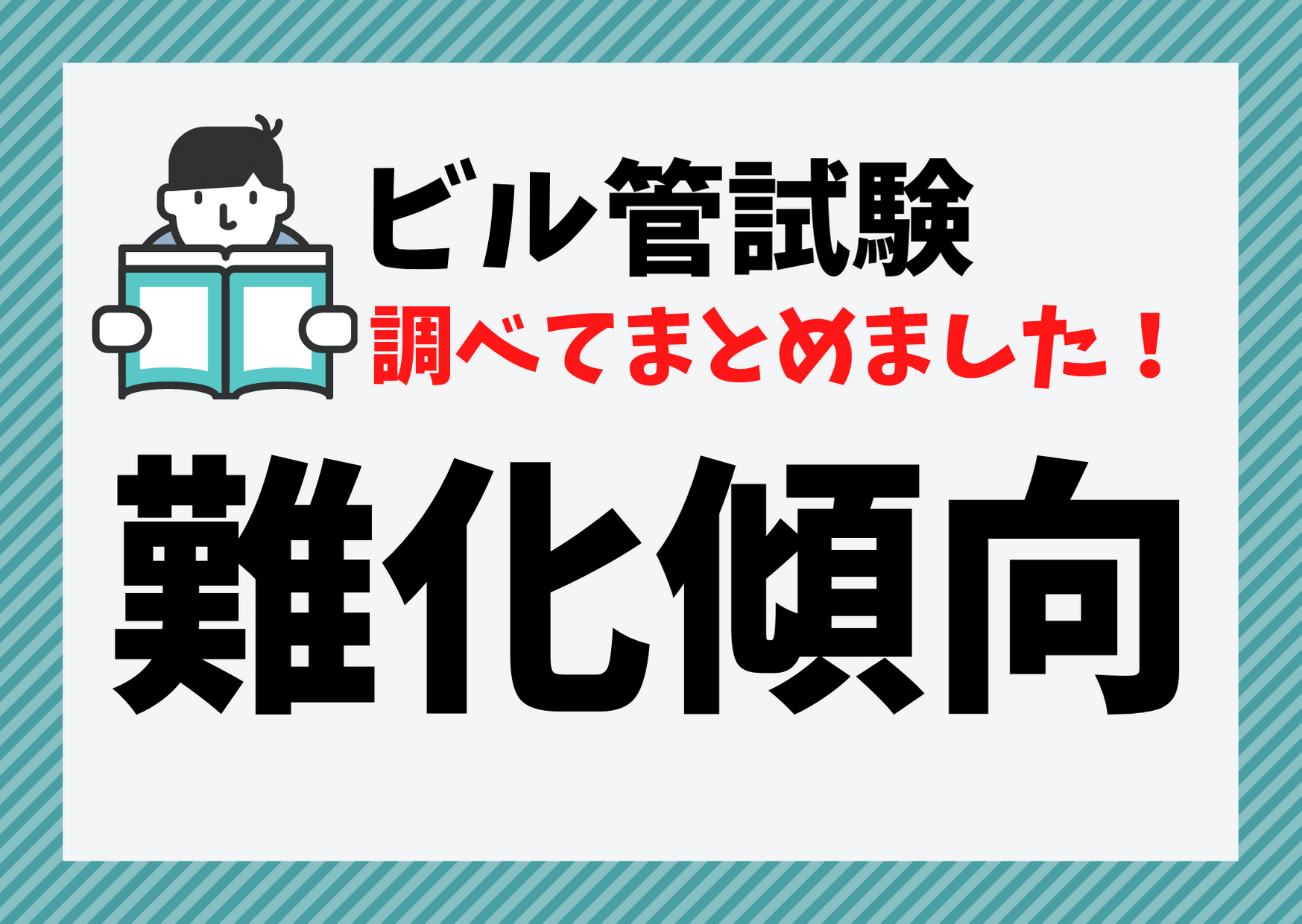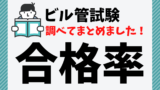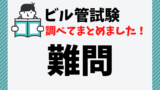ビル管試験の難化傾向とは
次はビル管試験の難化傾向について解説していきます。
難化とは試験問題が難しくなることを指します。(易化はやさしくなることを指します。)
難化するとどうなるか
いままで出題されていた問題から一歩踏み込んだ問題や、細かい数字、仕組みを理解していないと解答できない問題が出題されます。
また、過去出題されていない分野の問題(解説上「難問」と表記させていただきます。)も各科目で何問か出題されるので、自信をもって解答できない場面がでてきます。
実際の問題で解説します。
2020年・建築物の環境衛生より出題
暑さ指数(WBGT)は、屋内や屋外で太陽放射がない場合、0.7TA+0.3TBで求められる。ただし、TAは■、TBは□である。正しい組み合わせはどれか。
- 誤:■黒球温度、□湿球温度
- 誤:■湿球温度、□乾球温度
- 正:■湿球温度、□黒球温度
- 誤:■乾球温度、□黒球温度
- 誤:■乾球温度、□湿球温度
なんとなくの暗記では解答できない問題が出る。
WGBT(湿球黒球温度)については、「黒球温度と湿球温度の組み合わせによる熱中症予防のための指標」が、いままでの試験で必要な知識でした。しかし、太陽放射がない場合のWGBT式の組み合わせまで踏み込まれ出題されました。TW、TGの表記であれば「W:湿球、G:黒球」と分かるのですが、問題文からはわからないため、正確に理解していなければ選択肢1と選択肢3で悩む問題です。細かい知識まで理解していないと選択肢を絞り切れず、あと一歩自信を持って解答することができません。
また、温熱環境指数(温熱指標)は他にも種類があるため「どれを」「どこまで」「深く」勉強すればいいのか悩ましいところです。不快指数(DI)にも「気温と乾球温度」「気温と相対湿度」の式が細かくそれぞれあります。(2020年度は合格率19.5%の年度でしたが、一歩踏み込んだ問題の解説としてWGBT問題を使用しています。)
直近5年間の難化傾向について(重要)
全体的な試験問題の難化というよりは、特定科目での難化が見られます。
また、近年では特に、出題数の少ない科目で難化傾向が見られ、出題数の多い科目では易化により点数を稼ぎやすくなっています。
つまり、総合点は取りやすいのですが、科目落ちしてしまう恐れがある傾向にあります。
具体的な科目を挙げるならば、
難化傾向の科目
- 建築物衛生行政概論(20問)(2022年度に難化)
- 建築物の構造概論(15問)(2021年度に難化)
- ねずみ・昆虫等の防除(15問)
易化傾向の科目
- 建築物の環境衛生(25問)
- 空気環境の調整(45問)
- 給水及び排水の管理(35問)
- 清掃(25問)
個人差はあると思いますが、以上のような傾向にあると思います。
特に注意したいのは「建築物の構造概論」「建築物の構造概論」が難化傾向にあるということです。
細かい知識まで必要な問題が多いです。かつ、難問も出題されます。
難化傾向の問題点
「建築物の構造概論」「建築物の構造概論」の出題数は少ないため、
1問1問が合否に大きく影響します。
過去問に出題されてこなかった分野の問題が5~6問出題される年度もあります。受験体験記を他人事だと思わず、事前にしっかりと対策をしておくべき科目です。
ビル管試験の難問について
次はビル管試験の難問について、実際の問題をみながら解説していきます。